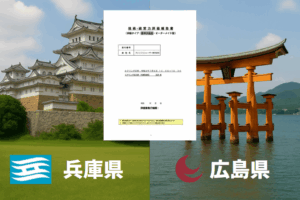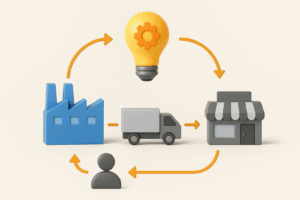会社の強さは、数字の外側に本当にあるのか?
ここまで、富松中小企業診断士が技術・経営力評価書の概要と書き方について説明してくれました。
ここからは実際の運用の場面で、注意した方が良いと考えていることを書いています。企業評価の仕事に携わるなかで、私はいつも一つの葛藤を抱えています。それは「数字だけを見ていては企業の本当の姿は見えない」と分かっていながら、実務の多くが成果や結果に縛られてしまうという現実です。
私はこの制度に深くかかわり、時には中小企業診断士として評価書作成者となり、時には評価委員として評価書の妥当性を審議する側にいたりしました。この制度を追求していくなかで、避けられないジレンマに直面してきました。その点に触れ、何をどう悩んだのか、どうあることが望ましいのか、を書いています。皆様のご理解の一助になればと願っております。
数字に表れていない(今後表れると期待される)会社の能力
数字では測れない力をどう表すのか。本当はそこにこそ競争力が潜んでいると感じながらも、成果や結果(決算数値や取引先数など)から逃れられない難しさを常に感じています。
例えば売上高・利益高が低い場合、優位性や事業遂行能力を証明することは妥当でないと判断されやすいです。
また、極めて稀有で突出して高い技術力も、市場に求められていない場合には技術力と認めるべきなのかどうか?市場が知らないだけで販売方法を強化すれば大きく会社が飛躍するような技術かもしれませんが、現時点で発揮されていない(収益につながっていない)ものであれば高く評価することはできません。
本来、ポテンシャル(潜在的能力)も加味して評価することが事業性評価の有意義な点であると考えていますが、数字の外側にあるものを科学的・合理的に証明することは極めて難易度が高く、評価の点数に反映し辛いと言えます。
それでも数字だけでは判断できない
確かに定量的なデータは客観的で比較可能ですが、それだけで企業の競争力を十分に評価できるわけではありません。むしろ、数字に表れない領域にこそ、その会社らしい強みや成長力が潜んでいることが少なくありません。
定性評価の難しさ
ここまでご覧いただいている皆様はすでにご承知であると思いますが、定性評価とは、経営者の姿勢、現場の士気、組織文化といった、数値化が難しい領域を見極めて表現するものです。ただし、「定性評価はどうしても主観が入りやすいという危うさ」を抱えています。私のような中小企業診断士であっても、主観を完全に捨てることはできません。
主観は「専門性の証」
しかし、だからといって主観を排除してしまえば、専門性を活かせない評価にとどまってしまいます。むしろ、経験や知見に裏打ちされた「整理された主観」こそ、専門家が発揮できる価値だと考えています。
市場を動かす非合理の力
現実には、市場で強い訴求力を持つのは、必ずしも合理的に説明できる要素だけではありません。「この会社と一緒にやりたい」「この製品には惹かれる」といった印象の背景には、優しさや情熱、衝動、常軌を逸しているとも思える製品への愛といった「非合理」なものが大きな役割を果たします。そして、それが結果として競争優位を支えているケースは多々あります。
事業性評価は翻訳である
成果・結果に縛られる現実
企業評価の現場では、どうしても「成果」や「結果」といった目に見える数字から判断せざるを得ない場面が多いのも事実です。本当は、その成果に至るまでの取り組みや組織の努力こそ評価したいのですが、それを数字以外の形で伝えることは容易ではありません。そのため、評価が成果・結果中心になってしまうのは、ある意味で必然でもあります。
大切なのは、その限界を自覚したうえで、数字に表れにくい価値をどう補完的に伝えていくかです。完全に成果主義の枠組みから脱却することは難しくても、定性評価によって「未来に向けた可能性」を合理的に表現することは十分に可能です。
非合理を合理に翻訳する
問題は、その非合理をどう表現するかです。単に「人柄がいい」「雰囲気がいい」と書いても説得力は生まれません。そこで必要になるのが、合理的な言葉への「翻訳」です。たとえば「社員が笑顔で働いている」という印象を、「離職率が低く、安定した人材確保につながっている」と表現すれば、金融機関や取引先にも伝わる評価になります。
ピンカーの合理性と定性評価
スティーブン・ピンカーは著書『Rationality(合理性)』の中で、人間は必ずしも合理的に行動する存在ではない一方で、合理性という道具を持ち、それを通じてよりよい判断に近づけると述べています。定性評価もこれと同じで、非合理な力を排除するのではなく、合理的な言葉に置き換えることで評価の一部として活かすことができます。
ここで重要なのは、「非合理性の効果」を説明する営みそのものは、必ず合理的に行わざるを得ないという点です。たとえば「社員の情熱が競争力につながっている」と感じても、それをそのまま書くのでは説得力に欠けます。「情熱 → 定着率の高さ → 技術力の蓄積」という因果関係に翻訳し、合理的なプロセスで説明する必要があるのです。
評価者(金融機関・支援機関・専門化)に求めたいこと
注意すべきものの見方
つまり定性評価とは、「非合理を合理に翻訳するプロセス」です。非合理な要素を見つけるだけでは不十分で、それを合理的に説明する営みを通じてはじめて評価となります。そして、現実には成果や結果に引っ張られてしまう限界があるとしても、その枠を少しでも広げ、未来を見据えた可能性を描くことに挑戦しなければなりません。
我々も皆様も、企業を見るときに注意すべきは、数字のみに依存しないことです。経営者の想いや社員の熱意、組織の一体感といった「見えにくい力」を、合理的な言葉に置き換えて理解すること。それこそが、未来に向けた成長可能性を見極めるために欠かせない視点だと思います。
我々の非合理性
最後に、我々や皆様が持つ「企業を支援したい」「そこで働くヒトの喜びを追求したい」という情熱もまた、合理だけでは説明できない非合理に根ざしているのではないでしょうか。その非合理こそが、企業と支援者の双方を突き動かし、未来を形づくっていくのだと感じています。
是非、この非合理的な情熱を忘れずに、絶対的である「数値」の先にあるものを合理的に表現する営みを続けていきたいです。我々が限界に気づいてなお、合理性を見出せないかと葛藤を続けていく中で、より良い事業性評価ツールが生まれると考えています。
やや精神的な寄稿ではありますが、常に意識をしておくことが肝要です。項目に沿ってヒアリング次項を列挙しているだけの評価書では企業は動けません。結果を生んでいる情念について、「なぜそうなのか?」と問いを立てなければなりません。
人がすることには思いがあります。思いを汲み取ったことが分かれば、指摘事項について、企業は改善に取り組んでくれます。「「思い」は非合理的で合理的に文章化することに限界があるが、そこに触れる挑戦をしなければ、事業性評価は効果的では無い」。技術経営力評価でも、他のツールでも、その点の留意を十分に持って挑めば、例え文章化ができなくとも、経営者との関係性は良好になります。
私見の多い寄稿となりましたが、是非ご参考にしていただければと願っています。