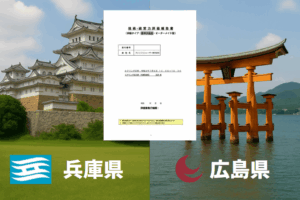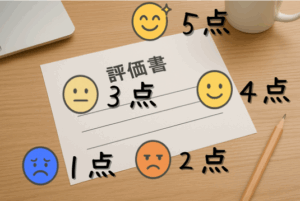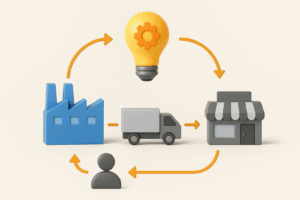前稿では、定性評価の重要性や「非合理な力」をどう見るかについて述べました。
しかし「抽象的すぎる」「実務でどう使えばいいのか」と思われた方もいるかもしれません。
そこで本稿では、金融機関・支援機関・専門家、そして中小企業の皆様が、実際の評価書作成および見方、様々な経営支援の現場で活用できるよう、非合理を合理に翻訳する手順を具体的にご紹介します。
定性評価を役立てるための3つの視点
非合理な力をどう発見するか
企業の現場には、数字だけでは測りきれない「熱」や「工夫」が存在します。
- 経営者の諦めない姿勢
- 熟練社員の暗黙知
- 新人の柔軟なアイデア
- 地域社会とのつながり など
これらは売上や利益の数字にはすぐに現れないため、軽視されがちです。しかし、実際には企業の競争力を下支えする大きな要因です。
診断士や金融機関職員は、ヒアリングや現場観察を通じて、こうした「一見非合理な力」を丁寧に拾い出す必要があります。
合理的な言葉にどう翻訳するか
「社員がやる気にあふれている」といった定性表現は、読んだ側にとっては単なる印象論に過ぎません。
そこで重要になるのが翻訳です。
- 「社員がやる気にあふれている」
→ 「過去3年間の離職率が業界平均の半分以下」
→ 「現場の改善提案件数が前年比120%で増加」
このように、主観的な観察や感覚を、客観的なデータや行動に置き換えることで、評価に説得力が生まれます。
翻訳とは、現場で感じ取った非合理的な力を、金融機関や外部関係者に伝わる形へ変換する作業なのです。
数値とどう補完し合うか
数字だけでは会社の未来は語れません。しかし、数字抜きでは説得力がありません。
定性と定量は車の両輪であり、組み合わせることで初めて企業の真の姿が浮かび上がります。
- 定性:未来の芽を示す(情熱・姿勢・文化)
- 定量:過去と現在の結果を示す(売上・利益・シェア)
例えば「技術者が誇りを持っている」という定性情報だけでは不十分です。
そこに「不良率1%未満を3年間維持」という定量を添えれば、金融機関も納得しやすくなります。
翻訳の具体例
技術力
定性:「高度な加工技術を持つ」
翻訳:「独自治具を開発し、不良率を5%→1%未満に低減。主要取引先から認定」
人材
定性:「社員の士気が高い」
翻訳:「離職率が業界平均の半分以下、技能伝承も継続、新人も1年で戦力化」
組織文化
定性:「改善意識がある」
翻訳:「改善提案件数が前年比120%増、70%が採用され生産性向上に寄与」
このように翻訳することで、「数字の裏にある力」を理解しやすくなりますし、経営者自身も「自社の強みを合理的に把握できる」効果が生まれます。
「まだ数字に出ていないが、いずれ成果に結び付く」事例集と対応質問リスト
<参考>事例と質問リスト
人材・組織
- 事例:「入社3年未満の社員が毎月改善提案」→ 今は売上に直結していないが、将来の生産性向上に結び付く。
- 事例:「女性社員の管理職登用」→ 収益には影響しないが、多様性が人材定着率を高める。
質問
□ 若手社員の提案は出ていますか?
□ 離職率や人材定着の状況は?
□ 多様な人材の登用は進んでいますか?
技術・製品
- 事例:「新しい溶接工法を特許出願中」→ 特許認定後は独自優位性を確立できる。
- 事例:「展示会で大手小売から高評価」→ 将来の売上増につながる可能性が高い。
質問
□ 特許出願や技術認定の準備はありますか?
□ 展示会での評価や取引先からの反応は?
市場・顧客
- 事例:「大手メーカーと試験導入を開始」→ 本契約は未確定だが、成功すれば長期安定取引先の獲得につながる。
- 事例:「東南アジア展示会で20件の商談依頼」→ 輸出売上はまだゼロだが、新市場開拓の芽として有望。
質問
□ 新規顧客との試験契約は進んでいますか?
□ 海外からの引き合いや問い合わせは増えていますか?
経営姿勢・文化
- 事例:「生産管理システムを導入しデータ収集を開始」→ 数値改善はこれからだが、在庫削減やリードタイム短縮に直結する。
- 事例:「地元高校とのインターン受け入れ」→ 今の利益には現れないが、採用基盤強化や地域ブランド向上につながる。
質問
□ DXやシステム導入の準備状況は?
□ 地域社会との連携や人材育成の取り組みは?
横断的質問
□ 今はまだ数字に出ていないが、「将来必ず成果になる」と信じている取り組みはありますか?
□ 「この強みが将来の競争力になる」と思うものは何ですか?
□ 社員や現場から「これは誇れる」とよく言われることはありますか?
□ 今後3~5年で数字に表れると考えている成果は何ですか?
リスト利用の注意点
上記質問リストはほんの一部を示したものです。質問リストを事前に準備することは非常に有効ですが、同時にいくつかの危険性も伴います。
- 形骸化のリスク:質問に沿うだけでは「作業」となり、本音が出にくい
- 誘導リスク:聞き方次第で回答が実態以上に良く見える
- 思考停止リスク:チェックしただけで満足せず、必ず「なぜ?」と掘り下げる
リストは「入口」にすぎません。そこから深掘りして初めて評価情報になります。
実務で使える定性表現に対するチェックリスト
<参考>定性評価チェックリスト
- 表現の妥当性
□ 「雰囲気がいい」「社員が頑張っている」など曖昧な言葉にとどまっていないか?
□ 読み手が「具体的にどういう状況なのか」をイメージできる表現になっているか? - 客観的裏付け
□ 定性情報を裏付けるデータ(数値、指標、第三者評価、事例)が添えられているか?
□ 過去の実績や具体的な行動履歴を示しているか?
□ 「一時的な印象」ではなく「持続的な傾向」であることを説明できているか? - 因果関係の明確化
□ その非合理な要素が「どのように成果や競争力につながるか」を説明しているか?
□ 「情熱 → 離職率低下 → 技術力の蓄積」など、論理の流れが明示されているか?
□ 読み手が「なるほど、だから競争力があるのか」と納得できる構造になっているか? - 読み手への伝わりやすさ
□ 専門用語に偏らず、金融機関や第三者でも理解できる言葉で表現しているか?
□ 数字と文章のバランスが取れているか?
□ グラフや表で補足できる部分は可視化しているか? - 定量との補完関係
□ 数字に現れていない強みを、将来の数値成果と結び付けているか?
□ 定性評価と定量評価が矛盾していないか?
□ 「まだ数字に出ていないが、いずれ成果に結び付く」ことを合理的に示せているか? - 実務的な活用可能性
□ 融資判断や経営改善の材料として、読み手が「アクションを取れる情報」になっているか?
□ 経営者自身が自社の強みを再認識し、行動につなげられる内容になっているか?
□ 読み手が「参考にはなるが動けない」と感じる自己満足的な文章になっていないか?
4. 定性評価の活用で実現できる未来
- 金融機関にとって
数字だけでは判断できない「未来の伸びしろ」を把握でき、融資判断の質が高まる。 - 支援機関にとって
支援先の潜在力を理解することで、的確な施策提案やマッチングにつながる。 - 企業経営者にとって
自社の強みを「合理的な言葉」で知ることができ、経営戦略や従業員教育に活用できる。
定性評価を実務に落とし込むことは、単なる評価作業ではなく、企業と金融機関・支援機関の信頼関係を深めるプロセスでもあります。
定性評価は「非合理を合理に翻訳する」営みです。
翻訳には訓練と工夫が要りますが、事例・質問リスト・チェックリストを増やしていけば、確実に「使える道具」にできます。※くどいようですが、個人の思いや情熱はリスト化できません。リストはあくまでも入口です。
ぜひ皆様の現場で、この翻訳作業を実践していただきたいと思います。膨大な数のトライ&エラーによって精度は上がっていきます。ただし、我々支援サイドにいる者は実際の企業を相手にエラーを出すことが許されません。そのため、日頃の思考のトレーニングを続けていくことで、能力を留めるだけではなく、漸進的でも良いので発展させていく必要があります。
自分なりの質問リストを作成してみて、そのリスト自体を見せ合って評価し合うなど、訓練を続けていく心構えを持ちたいです。その一助に本記事が役立てば何よりです。