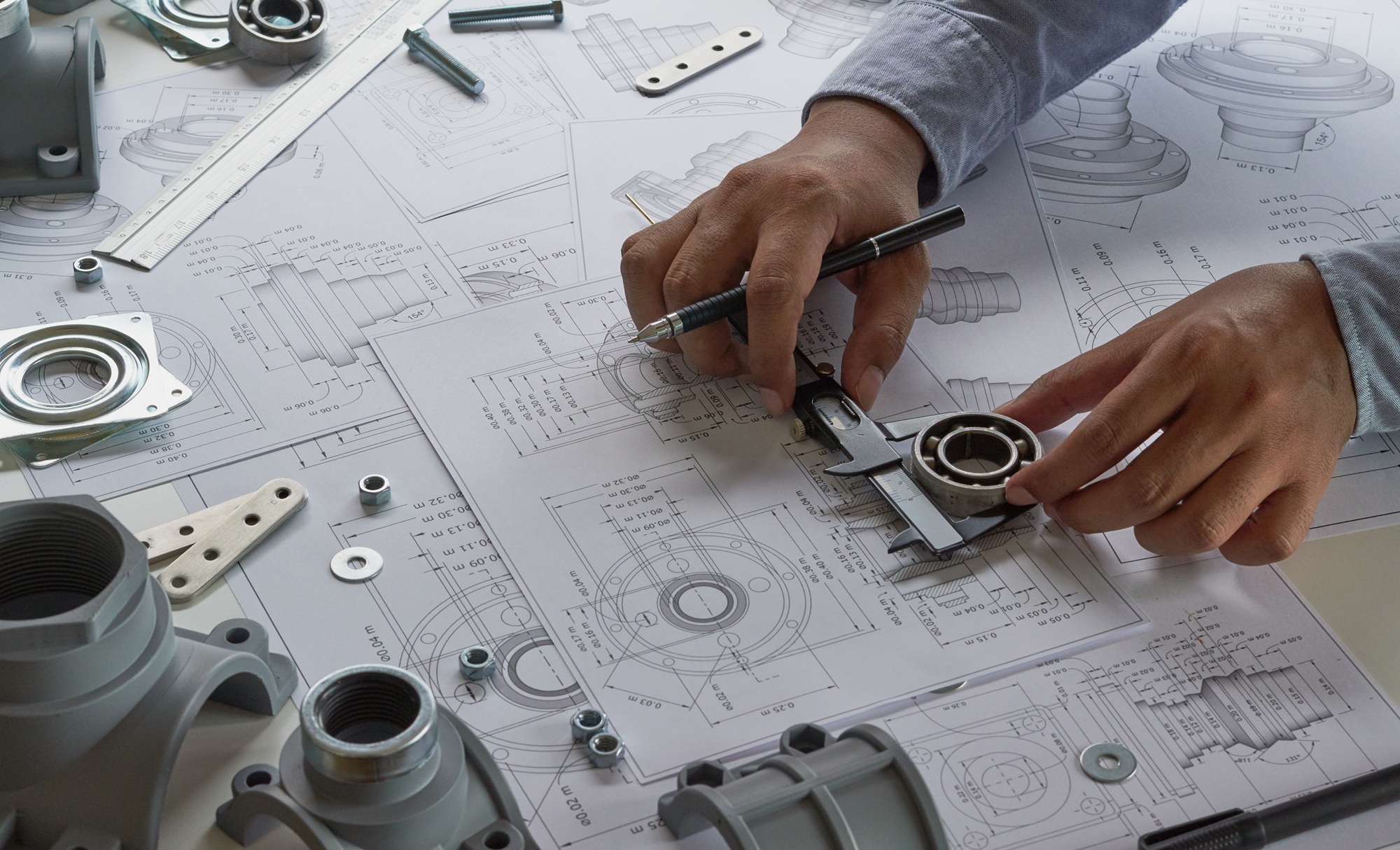日本の企業金融が、歴史的な転換点を迎えています。
2026年までに施行が迫る「事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)」。これは単なる一つの法律の誕生ではありません。長年にわたる不動産担保や経営者保証に依存した融資慣行を改め、企業の「事業そのもの」の価値、すなわち事業性を評価し、未来の成長可能性に資金を供給する――。そんな未来志向の金融への、国を挙げた号砲です。
この変革の波は、私たち金融支援の現場にいるすべての関係者にとって、決して他人事ではありません。
- 金融機関の事業支援ご担当者様は、「事業性評価の基準をどう作り、実務に落とし込むか」「新しい担保権のリスク管理はどうすれば?」といった課題に直面されていることでしょう。
- 中小企業の経営者様は、「自社の技術やブランドといった『見えない価値』をどう伝えれば資金になるのか」「本当に経営者保証から解放されるのか」といった期待と不安が入り混じっているかもしれません。
- そして、両者を支える中小企業診断士をはじめとする専門家の皆様は、「この新制度をどう活用し、クライアントの成長に貢献できるか」という新たな支援手法を模索されているはずです。
私たち「事業性評価ツール研究会」*は、事業性評価の最前線で活動する中小企業診断士の専門家チームです。日々、客観的な評価ツールと実践的な知見を基に、企業の価値を「見える化」するお手伝いをしています。
だからこそ今回は、私たちの専門的見地から、この「事業性融資推進法」の全容、特にその核心である「企業価値担保権」の仕組みから実務上の要件、そして各々の立場で今から何を準備すべきかまで、どこよりも分かりやすく、かつ深く掘り下げて解説します。
ぜひこの目前に迫った大きな変化をチャンスと捉え、具体的な次の一歩を踏み出すための、明確な羅針盤が手に入れるため、以下の3つの重要ポイントから把握してみてください。
まずはコレだけ!事業性融資推進法の3つの重要ポイント
複雑に見えるこの法改正ですが、押さえるべき核心はシンプルです。今回は、特に以下の3つの重要ポイントに焦点を当て、この歴史的な変革を紐解いていきます。これを読むだけで、この先の議論の全体像がクリアになるはずです。
ポイント1:融資の”常識”が変わる!「担保・保証」から「事業の価値そのもの」へ
最初のポイントは、日本の企業金融における「ゲームチェンジ」です。これまで当たり前だった不動産担保や経営者による個人保証への過度な依存から脱却し、企業の持つ技術力、ブランド、顧客基盤、そして将来性といった「事業そのものの価値(事業性)」を正当に評価して融資を行おう、という大きな方針転換が明文化されました。これは、すべての企業と金融機関にとって、融資に対する考え方を根本から見直す必要があることを意味します。
ポイント2:事業を”まるごと”担保に!新設「企業価値担保権」の衝撃
この法改正の最大の目玉が、全く新しい担保の概念である「企業価値担保権」の創設です。これは、土地や建物といった個別の資産だけでなく、知的財産やノウハウなどの無形資産、将来生み出すキャッシュフローまで含めた「事業全体」を一体として担保にするという画期的な仕組みです。これまで資金調達が難しかったスタートアップやサービス業など、多くの企業に新たな可能性の扉を開きます。
ポイント3:もはや他人事ではない!立場別にわかる「今すぐすべき準備」がある
この変革は、ただ待っていれば恩恵を受けられるものではありません。企業は自社の価値を「見える化」し、金融機関は事業を見る「目利き力」を磨き、私たち専門家は両者を繋ぐ新たな支援策を講じる必要があります。本記事の後半では、「企業」「金融機関」「専門家」それぞれの立場で、2026年の施行に向けて具体的に何を準備すべきか、明日から取り組めるアクションプランを詳しく解説します。
では早速、詳しく解説していきましょう。
そもそも事業性融資推進法とは?わかりやすく解説
先の3つのポイントで、今回の法改正が大きなインパクトを持つことをお伝えしました。では、そもそもなぜ今、このような法律が必要になったのでしょうか。その背景と目的を理解することが、新時代の金融支援を読み解く第一歩となります。
なぜ今、この法律「事業性融資推進法」が必要なのか?制定の背景
この法律は、決して机上の空論から生まれたわけではありません。私たち専門家が日々向き合っている、企業金融の現場にある切実な「課題」から生まれています。
課題1:不動産担保・経営者保証に依存した融資の限界
「担保となる不動産がないと、融資は難しい」「万が一に備え、経営者の方に個人で保証していただくのが慣例です」――。金融機関のご担当者様なら、これまで何度も使われてきた言葉ではないでしょうか。そして経営者の皆様は、この言葉に悔しい思いをされた経験があるかもしれません。
この長年の融資慣行は、金融機関にとって債権保全の確実性を高める一方で、将来性のある企業の挑戦にブレーキをかけ、経営者に過大なリスクを負わせてきました。この構造的な課題に、国として本格的にメスを入れる必要があったのです。
課題2:スタートアップや無形資産を持つ企業の成長支援
現在の日本経済を牽引するのは、もはや工場や設備といった有形資産だけではありません。独自のソフトウェア、優れた技術、魅力的なブランド、強固な顧客基盤といった「目に見えない資産(無形資産)」こそが、多くの企業の価値の源泉となっています。
しかし、従来の金融のモノサシでは、こうした無形資産の価値を正しく測り、融資につなげることが困難でした。その結果、素晴らしいアイデアや技術が「宝の持ち腐れ」になるケースも少なくありません。この法律は、新しい時代の価値を正当に評価し、成長のエンジンとなる資金を供給するための、新しい金融インフラを目指しています。
課題3:事業承継・事業再生の円滑化
「会社は継ぎたいが、先代の莫大な個人保証まで引き継ぐのは怖い」。これは、私たちが支援する事業承継の現場で頻繁に耳にする、後継者の本音です。経営者保証が、円滑なバトンタッチを阻害する大きな壁となっているのです。
また、一度経営が傾いた企業が再チャレンジしようとする際も、保証の存在が迅速な事業再生の足かせとなることがあります。この法律は、経営者個人のリスクを切り離すことで、事業という価値ある資産を次世代へ、あるいは再起の道へとスムーズにつなげる役割も期待されています。
事業性融資推進法が目指すゴールと主な対象事業者
こうした背景を踏まえ、法律の第一条では、その目的が明確に示されています。
事業性融資推進法が目指す4つの目的(第一条)
専門的な条文を、私たちなりに解釈すると、以下の4つのゴールが掲げられています。
- 担保や個人保証に頼りすぎた融資の慣行を正すこと
- 会社の事業に必要な資金調達をスムーズにすること
- 会社の事業の継続と、さらなる成長・発展をサポートすること
- これらを通じて、日本経済全体の健全な発展に貢献すること
特に恩恵を受けるのはどんな会社?
この法律の恩恵はすべての企業に及びますが、特に以下のような企業にとっては、大きな追い風となるでしょう。ご自身の会社、あるいは支援先の企業が当てはまるか、チェックしてみてください。
- 有形資産に乏しいスタートアップ(IT、SaaS、コンテンツ制作など)
- 知的財産やブランド価値が競争力の源泉である企業(研究開発型、デザイン会社など)
- 経営者の個人保証がネックで事業承継が進まない企業
- 経営の立て直しを図る、事業再生に取り組む企業
国の推進体制:金融庁の「事業性融資推進本部」と「認定支援機関」の役割
国がこの変革に「本気」であることは、その推進体制からも見て取れます。
一つは、金融庁に設置される「事業性融資推進本部」です。金融担当大臣をトップに、経済産業省や法務省など関係省庁の大臣クラスが集う、まさに「司令塔」。法律を作って終わりではなく、国全体で強力に推進していくという強い意志の表れです。
そしてもう一つ、私たち専門家にとっても重要なのが「認定事業性融資推進支援機関」制度です。これは、司令塔からの指示を現場で実行する、いわば「専門家パートナー」を国が認定する仕組み。私たち中小企業診断士や会計士などが、企業の事業価値評価や説得力のある事業計画の策定を具体的にサポートし、企業と金融機関の「橋渡し役」を担うことが期待されています。
このように、法律の背景と全体像を理解することで、次の核心部分である「企業価値担保権」がなぜ必要とされたのか、より深く理解できるはずです。
【本法律の核心】全く新しい担保「企業価値担保権」を徹底解剖
さて、ここからは本法律の最大の目玉であり、私たち専門家が最も注目している「企業価値担保権」について、その仕組みから具体的な手続き、そして万が一の時のことまで、徹底的に解剖していきます。この新しい担保権を理解することが、新時代の資金調達を制する鍵となります。
企業価値担保権とは?その画期的な仕組み
まずは、この新しい担保権が一体どのようなものなのか、その概念の核心から掴んでいきましょう。
不動産や在庫だけでなく「事業そのもの」を担保にする考え方
従来の担保は、土地や建物、機械設備といった「個別の資産(パーツ)」を対象としていました。しかし企業価値担保権は、全く発想が異なります。
例えるなら、会社を「利益を生み出し続ける一つの生命体」として捉え、その生命体そのものを丸ごと担保にするイメージです。そこには、財務諸表に載っている資産だけでなく、これまで評価が難しかった以下のような「目に見えない価値」も含まれます。
- 知的財産:特許、著作権、ソフトウェアのソースコードなど
- ブランド価値:長年かけて築き上げた知名度や信頼
- 人的資産:優秀な従業員チームや独自の組織文化
- 顧客基盤:優良な顧客リストや強固な取引関係
- 将来キャッシュフロー:将来的に事業が生み出すと予測される収益
つまり、「私たちの会社には不動産はないけれど、どこにも負けない技術と顧客からの信頼がある」――。そんな企業の真の価値を、資金調達に直結させる道が開かれたのです。
既存の抵当権や企業担保権との違い(比較表)
「事業全体を担保にする」と聞くと、既存の「企業担保権」を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、両者は似て非なるものです。ここで、代表的な担保権との違いを整理してみましょう。
| 特徴 | 企業価値担保権(新法) | 不動産抵当権(民法) | 企業担保権(旧法) |
| 担保対象 | 会社の総財産(無形資産・将来収益含む) | 特定の不動産 | 会社の総財産(ただし対象は限定的) |
| 設定方法 | 信託契約+商業登記 | 設定契約+不動産登記 | 公正証書+商業登記 |
| 事業活動への影響 | 通常の事業活動は自由。事業継続が重視される。 | 原則自由 | 一定の制限あり |
| 実行方法 | 管財人による「事業譲渡」が原則 | 競売による売却が原則 | 管財人による管理・換価 |
特に重要なのは、担保対象の広さと、万が一の際の実行方法です。企業価値担保権は、事業の価値を破壊する「解体・切り売り」ではなく、事業を活かしたまま再生させる「事業譲渡」を原則としている点が、決定的に異なります。
なぜ「信託契約」が必要なのか?三者構造の役割
この制度のもう一つの特徴が、少し複雑な「信託」の仕組みを利用する点です。「なぜ融資を受ける金融機関と直接契約しないの?」と疑問に思われるかもしれません。
これには、担保価値を客観的に管理し、万が一の際の手続きを公正に進めるという重要な目的があります。登場人物は以下の三者です。
- 委託者:会社(債務者)
- 受託者:国の免許を受けた信託会社(担保権者)
- 受益者:お金を貸す金融機関(債権者)
会社は、自社の事業全体を「信託財産」として、中立的なプロの管理人である信託会社に託します(信託契約)。信託会社は、その事業価値を客観的に管理し、お金を貸している金融機関のために担保権を保有します。この仕組みにより、貸し手の一方的な都合で担保権が実行されるのを防ぎ、企業の事業継続と、すべての利害関係者の利益を守る機能が期待されているのです。
企業にとってのメリット・デメリット
この画期的な仕組みは、企業に大きなチャンスをもたらしますが、同時に注意すべき点もあります。双方を理解した上で、活用を検討しましょう。
メリット
- メリット1:担保にできる資産の範囲が広がる(無形資産・将来の収益)ソフトウェア開発会社ならプログラム、飲食店なら秘伝のレシピや顧客台帳、製造業なら熟練工の技術ノウハウ。これらすべてが、資金調達のための価値ある資産となり得ます。
- メリット2: 不動産がなくても大規模な資金調達が可能に「事業には絶対の自信があるのに、土地がないから…」と諦める必要はもうありません。事業の将来性や収益力をきちんと示すことができれば、大規模な成長資金を確保できる可能性があります。
- メリット3: 原則、経営者保証が不要になる事業全体で十分に価値を担保するため、経営者個人がリスクを負う必要がなくなります。これにより、経営者は思い切った事業展開に挑戦でき、後継者も安心して事業を引き継げます。
- メリット4: 事業を続けながら融資を受けられる担保設定後も、仕入れや販売、設備の入れ替えといった「通常の事業活動」は、これまで通り自由に行えます。事業運営に支障をきたすことはありません。
デメリット
- デメリット1: 制度が複雑で、専門家の支援が必要になる可能性信託契約や事業価値の評価など、手続きは決して簡単ではありません。だからこそ、本制度の活用には、私たちのような専門家と二人三脚で取り組むことが成功の鍵となります。
- デメリット2: 信託報酬などのコストが発生する専門家である信託会社に管理を依頼するため、その対価として信託報酬が必要になります。また、事業価値評価を外部の専門家に依頼する場合、その費用も考慮する必要があります。
- デメリット3: 登記により、取引先から信用不安と見られるリスク企業価値担保権を設定すると、会社の登記簿にその旨が記載されます。これを取引先が見た際に、「経営が苦しいのでは?」と誤解されるリスクはゼロではありません。しかし、見方を変えれば「国が認めた新しい制度を活用し、成長投資に挑んでいる先進的な会社」というポジティブなシグナルにもなり得ます。
企業価値担保権を設定するための重要要件
この強力な担保権は、誰でも自由に設定できるわけではありません。制度の信頼性を保つため、法律で以下の4つの重要な要件が定められています。
①「信託契約」が必須
先述の通り、設定は必ず「企業価値担保権信託契約」という特別な契約によって行われます。当事者間の合意だけでは成立しません。
② 免許を持つ「信託会社」との契約が必要
契約の相手方(受託者)は、財務基盤や専門性について国の厳しい審査をクリアし、免許を受けた「企業価値担保権信託会社」に限定されます。
③「商業登記」が効力発生の条件
契約を締結するだけでなく、法務局で会社の登記簿に「企業価値担保権設定」の登記を行って、初めて法的な担保権としての効力が生じます。これにより、第三者にも担保の存在が公示されます。
④ 他人のための担保設定は禁止
この制度は、あくまで自社の事業価値によって資金調達するためのものです。例えば、親会社が子会社の債務のために自社に担保を設定する、といったこと(物上保証)は認められていません。
企業価値担保権を設定するまでの手続きと流れ
では、実際にこの担保権を活用する場合、どのようなステップを踏むのでしょうか。大まかな流れは以下の通りです。
STEP1: 金融機関・専門家への相談
まずは、取引のある金融機関や、私たちのような中小企業診断士、会計士などの専門家に相談することから始まります。「この新しい制度を使って、こんな事業に挑戦したい」という想いを伝えることが第一歩です。
STEP2: 事業価値評価と事業計画の策定
ここが最も重要なプロセスです。自社の無形資産を含めた事業価値を客観的なデータで「見える化」し、その価値が将来どのように収益に結びつくのかを、説得力のある事業計画に落とし込みます。ここは、私たち事業性評価の専門家が最も得意とする領域です。
STEP3: 信託会社との「企業価値担保権信託契約」の締結
事業計画を基に金融機関との融資交渉が進むと同時に、信託会社を選定し、信託契約を締結します。契約内容には、どの範囲の債権を担保するのか(被担保債権の範囲)などを定めます。
STEP4: 法務局での「商業登記」(効力発生要件)
契約締結後、司法書士などの専門家を通じて、法務局で企業価値担保権の設定登記を行います。この登記が完了した時点で、正式に担保権の効力が発生します。
もしもの時、どうなる?担保の実行手続と倒産時の扱い
最後に、金融機関にとっても企業にとっても最大の関心事である、「万が一、返済が滞ってしまった場合」についてです。ここにも、従来の担保とは大きく異なる思想が貫かれています。
原則は「事業譲渡」。事業と雇用を守りながら換価する仕組み
従来の不動産競売のように、資産をバラバラにして安値で売却する、という発想はありません。原則として、裁判所の監督の下、選任された管財人が事業そのものを一体として、新たなスポンサー等に売却(事業譲渡)します。これにより、事業の価値を最大限維持し、従業員の雇用や取引先との関係を守りながら、債権の回収を図ることを目指します。
裁判所の監督と管財人の役割
手続きはすべて、裁判所の厳格な監督下で行われます。また、事業経営や財産管理を行う管財人には、法律や会計、事業再生に詳しい専門家が選任され、公平かつ専門的な手続きが担保されます。
従業員の給与や取引債務はどうなる?(共益債権の優先)
事業を継続するために不可欠な費用、例えば、手続き開始後の従業員の給与や、重要な仕入先への支払いなどは**「共益債権」**として扱われます。この共益債権は、担保権を持つ金融機関への返済よりも優先して支払われます。これは、事業価値の維持と円滑な事業譲去を支えるための重要なルールです。
破産や民事再生手続との関係
もし会社が破産や民事再生といった倒産手続に入った場合でも、企業価値担保権は強力な権利として扱われ、多くの場合、この担保権に基づく実行手続が優先されます。ただし、具体的な調整はケースバイケースとなるため、専門家との詳細な協議が必要です。
以上が、企業価値担保権の全体像です。非常に強力で可能性に満ちた制度ですが、その分、仕組みも複雑です。次の章では、この変革が各々の立場にどのような影響を与え、具体的にどう対応すべきかを解説していきます。
【立場別】新法施行に向けて今から準備すべきこと
ここまで法律の仕組みや可能性について解説してきましたが、この変革は座して待つだけではチャンスになりません。2026年までの施行というタイムリミットが迫る今、それぞれの立場で具体的な準備を始めることが不可欠です。ここでは、「企業」「金融機関」「専門家」の皆様が、今すぐ取り組むべきアクションプランを提案します。
企業(特に中小企業・スタートアップ)が準備すべきこと
経営者の皆様にとって、この法律は自社のポテンシャルを最大限に引き出すための強力な武器となり得ます。その武器を使いこなすために、まずは足元から固めていきましょう。
事業価値の「見える化」:自社の強みを言語化・数値化する
「我が社の強みは、長年の信頼と従業員の頑張りです」――その想いは非常に尊いですが、融資のテーブルでは客観的な言葉と数字が求められます。自社の技術のどこが新規的なのか、顧客のリピート率は何%か、ブランドが売上にどう貢献しているのか。まずは自社の「見えない価値」を一つひとつ棚卸しし、誰にでも伝わる形に翻訳する作業から始めてみてください。
事業計画の高度化:将来のキャッシュフロー予測とその根拠を明確にした計画を策定する
「売上を毎年10%伸ばします」という目標だけでは不十分です。「どの市場で、どの製品を、どのような戦略で販売するから、客単価と顧客数がこう変動し、結果として売上が10%伸びる」といった、物語と数字が連動した事業計画が不可欠です。なぜその成長が実現可能なのか、その根拠をロジカルに説明する力が、事業性評価の土台となります。
情報開示体制の整備:金融機関が評価しやすいように、財務・非財務情報を整理しておく
事業性評価は、一度きりのプレゼンテーションではありません。金融機関との継続的な対話、いわば信頼関係の構築です。そのためには、決算書などの財務情報はもちろん、月次の試算表や、開発の進捗、顧客満足度の推移といった非財務情報も、いつでも迅速に提示できる体制を整えておくことが重要です。これは、自社の経営管理レベルを向上させることにも直結します。
外部連携の検討:「認定事業性融資推進支援機関」等の専門家と早期に連携する
自社の価値を客観的に評価し、説得力のある事業計画を作成するのは簡単なことではありません。私たちのような中小企業診断士や会計士は、皆様の会社の「翻訳家」であり、「作戦参謀」です。早い段階から専門家と連携し、壁打ち相手として活用することが、新制度活用の成功確率を大きく高めるでしょう。
金融機関が準備すべきこと
金融機関のご担当者様にとっては、長年の与信文化を変革する、まさに挑戦の時です。お客様の成長を真に支援する「成長パートナー」となるために、以下の準備が急務となります。
事業性評価能力の向上:行員研修の実施や、新たな評価モデル・ツールを導入する
決算書の数字や担保価値を評価するスキルに加え、ビジネスモデルの優位性、市場の成長性、経営者の資質といった「事業そのもの」を見抜く「目利き力」がこれまで以上に求められます。実践的なケーススタディを用いた行員研修や、私たちのような専門家が開発する客観的な事業性評価ツールの導入が、その能力を底上げします。
リスク管理体制の再構築:新しい担保権に対応した与信審査プロセスや内部規程を整備する
新しい担保権の価値をどう算定し、与信判断に組み込むのか。モニタリングはどのように行うのか。自己資本比率規制上のリスクウェイトはどう考えるのか。個々の担当者のスキルアップだけでなく、組織全体として与信審査のプロセス、債権管理、内部監査に至るまでの規程やシステムを再構築する必要があります。
伴走支援体制の具体化:融資後のモニタリングや経営助言を行う体制と人材を育成する
「伴走支援」を単なるスローガンで終わらせてはいけません。融資先の事業計画の進捗を定期的に確認し、経営課題に対して的確なアドバイスを行う、あるいは適切な専門家を紹介するなど、具体的なアクションに落とし込むことが重要です。付加価値の高いリレーションシップバンキングを実践するための体制と人材育成が問われます。
実務オペレーションの整備:信託会社との連携や登記実務に関するマニュアルを準備する
企業価値担保権の実行には、信託会社との連携や、司法書士を通じた登記手続きなど、これまでとは異なるオペレーションが発生します。行内で混乱が生じないよう、具体的な手続きの流れ、必要書類、各部署の役割分担などを明記した実務マニュアルを早期に整備し、研修を行うことが不可欠です。
専門家(中小企業診断士・弁護士・会計士・税理士等)が準備すべきこと
最後に、私たち専門家自身がどう動くべきかについてです。この法改正は、クライアントの成長を本質的なレベルで支援する、まさに「腕の見せ所」です。特に、事業の全体像を捉え、未来戦略を描くことを本分とする中小企業診断士にとっては、その専門性を最大限に発揮できる、またとない機会となります。
法制度の完全理解:法律と「経営の実践」を結びつける翻訳者になる
法律・政省令・ガイドラインを読み解くのは当然の責務です。しかし、私たちの役割は、その法的要件を「では、クライアントの事業計画のどの部分を強化すればよいか」「金融機関が納得するストーリーをどう構築するか」といった、経営の具体的なアクションに翻訳してこそ価値が生まれます。法制度の理解を、クライアントの成長戦略に直結させることが求められます。
価値評価手法のスキルアップ:事業性評価ツールで「見えない価値」を客観化する
この新制度の成否は、無形資産や将来性といった「見えない価値」を、いかに客観的かつ論理的に評価できるかにかかっています。勘や経験則だけに頼る時代は終わりました。これからは、財務データと非財務データを統合的に分析し、事業のポテンシャルを多角的に評価する「事業性評価ツール」の活用が不可欠です。私たち研究会が提唱するように、こうしたツールを駆使して評価の客観性と説得力を高めるスキルこそが、これからの専門家の標準装備となるでしょう。
「認定支援機関」への登録準備:新時代の「公認パートナー」としての地位を確立する
国が設ける「認定事業性融資推進支援機関」は、新時代の企業金融における「公認パートナー」の証となります。多くの中小企業診断士は、既にものづくり補助金などで「認定支援機関」としての実績がありますが、この新しい認定は、事業性評価とファイナンスに特化した、より高度な専門性を示すバッジとなるはずです。いち早く要件を確認し、この重要な役割を担う準備を進めるべきです。
専門家ネットワークの構築:中小企業診断士が「ハブ」となり、チーム支援を主導する
ワンストップ支援の重要性は言うまでもありませんが、その中で中小企業診断士が「ハブ」となり、プロジェクト全体を指揮する役割が期待されます。事業戦略を描き、事業性評価で価値を明らかにした上で、法務面は弁護士、会計・税務面は会計士・税理士といった各分野のプロフェッショナルと連携する。私たちが全体のコンダクター(指揮者)となることで、クライアントに最高品質のチーム支援を提供できるのです。
よくある質問(Q&A)
ここでは、皆様からよく寄せられる質問や、今後想定される疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1. どんな無形資産が評価の対象になりますか?
A1. 法律で「これ」と限定されているわけではなく、「事業の収益に貢献する、目に見えない価値全般」が対象となります。
重要なのは、その無形資産が将来のキャッシュフローにどう結びつくのかを、論理的に説明できることです。具体的には、以下のようなものが考えられます。
- 【知的財産】
- 技術関連:特許権、ソフトウェアのソースコード、独自の製造ノウハウ、秘伝のレシピなど。
- ブランド関連:登録商標、サービスマーク、キャラクターデザイン、特徴的な店舗デザインなど。
- 【顧客関連資産】
- 顧客データ:優良な顧客リスト、CRM(顧客関係管理)システムに蓄積された購買データなど。
- 契約関係:大手企業との長期的な販売契約、安定した仕入れを可能にする供給契約など。
- 【組織・人的資産】
- 人材:熟練した技術者チーム、優秀な研究開発部門、定着率の高い従業員など。
- 組織文化:独自の開発プロセス、効率的な業務フロー、従業員のモチベーションを高める組織風土など。
これら一つひとつの価値を客観的に評価し、事業計画に落とし込む作業が、私たち専門家の腕の見せ所となります。
Q2. 企業価値担保権を設定すると、登記簿にどのように記載されますか?
A2. 会社の商業登記簿に、「企業価値担保権設定」という形で、その内容が公に記録されます。
会社の登記簿(登記事項証明書)は、法務局で誰でも手数料を払えば閲覧・取得できるため、取引先を含め第三者がその事実を知ることが可能です。
登記簿には、主に以下のような情報が記載されることになります。
- 「企業価値担保権設定」の事実
- 設定年月日
- 受託者(お金の貸し手である金融機関ではなく、管理を担う信託会社の名称)
- 極度額(融資の上限額)
- 被担保債権の範囲(どの範囲の借入を担保するのか)
デメリットとして「信用不安に見られるリスク」を挙げましたが、これは裏を返せば「国が認めた最新の制度を活用して、信託会社や金融機関から事業価値を認められた、成長意欲の高い会社」というポジティブな証明にもなり得ます。この事実をどう捉えるか、また取引先にどう説明するかが重要になります。
Q3. 融資を受けるための費用はどのくらいかかりますか?
A3. 一概には言えませんが、通常の融資に加えて、主に以下の3種類の費用が発生すると考えられます。
この制度は、大きな可能性を秘めている分、相応の専門的な手続きが必要となるため、コストも発生します。
- 【信託会社への費用】事業価値の客観的な管理と、万が一の際の手続きを担う専門家である信託会社に対して支払う「信託報酬」です。契約時の一時金や、融資期間中の年間手数料などが想定されます。
- 【専門家への費用】事業価値評価報告書の作成や、金融機関を納得させる事業計画の策定支援などを、私たちのような中小企業診断士や会計士に依頼する場合のコンサルティング費用です。融資の成功確率を高めるための「投資」と捉えることができます。
- 【実費】法務局に企業価値担保権を登記する際に必要となる「登録免許税」などの法定費用です。
これらの費用は、経営者保証を外せることや、これまで不可能だった大規模な資金調達を実現できるメリットと比較して、総合的に判断することが重要です。事前に金融機関や専門家に見積もりを相談することをお勧めします。
Q4. すでに他の融資を受けていても利用できますか?
A4. はい、原則として利用は可能ですが、「担保権の優先順位」の調整が必要となります。
多くの会社が、すでに不動産を担保に入れたり、別の融資を受けたりしているはずです。その場合、重要なのが「優先順位」です。
例えば、すでに工場に抵当権を設定している場合、万が一の際には、その工場の売却代金から、先に抵当権を持つ金融機関が返済を受ける権利があります。
今回新しく設定する企業価値担保権は、原則として、すでにある担保権よりも後の順位になります。ただし、この担保権の強みは、既存の担保の対象になっていない無形資産や将来収益など、事業のあらゆる価値を包含できる点にあります。
実務的には、新しい融資を行う金融機関が、既存の借入や担保の状況をすべて評価した上で、融資の可否や条件を判断することになります。場合によっては、既存の金融機関の同意を得たり、借換え(リファイナンス)を調整したりする必要も出てくるでしょう。既存の借入状況を含めて、正直に金融機関や専門家に相談することが、スムーズな手続きの鍵となります。
Q5. 専門家(中小企業診断士等)はどこで探せばよいですか?
A5. この分野は新しいため、「誰に相談するか」は非常に重要です。以下の窓口が考えられます。
- 【メインバンクや取引金融機関】金融機関自身も、この制度を推進するために専門家との連携を強化しています。まずは取引のある金融機関の担当者に相談してみるのが良いでしょう。
- 【商工会議所・商工会】地域の企業を支援する公的な団体です。専門家派遣事業などを通じて、相談に乗ってくれる専門家を紹介してもらえます。
- 【各都道府県の中小企業診断士協会】中小企業診断士の公的な団体で、会員の検索や紹介を行っています。事業性評価や資金調達に強い専門家を探すことができます。
- 【よろず支援拠点】国が全国に設置している無料の経営相談所です。様々な課題に応じて、適切な専門家につないでくれます。
- 【専門家からの直接の情報発信】私たち「事業性評価ツール研究会」のように、この分野に特化して情報発信を行っている専門家チームや事務所に、直接問い合わせてみるのも有効な手段です。
専門家を選ぶ際は、資格だけでなく、自社の業界への理解度や、事業への情熱を共有できるかといった「相性」も大切にしてください。
まとめ:事業性融資推進法は日本の金融を未来志向に変える号砲だ
ここまで、事業性融資推進法という大きな変革の背景から、その核心である「企業価値担保権」の具体的な仕組み、そして私たち一人ひとりが今から何をすべきかまで、詳しく解説してきました。
この法律は、単なる新しい融資制度の追加ではありません。それは、企業の価値を測る「モノサシ」そのものを、過去の資産から未来の可能性へと変える、日本の企業金融における歴史的なパラダイムシフトです。そして、その号砲は、もう鳴らされました。
この新しい時代のフィールドでは、それぞれのプレーヤーに新たな役割が与えられます。
- 企業の皆様へ。もはや「うちには担保がないから」と諦める必要はありません。皆様が日々汗を流して築き上げてきた技術、顧客からの信頼、従業員との絆といった「目に見えない価値」こそが、これからの時代、最強の資産となります。その価値を自信をもって語り、未来の事業計画として描く時が来たのです。
- 金融機関の皆様へ。バランスシートと不動産登記簿だけで与信を判断する時代は、終わりを告げようとしています。企業の未来に深くコミットし、その成長の物語を共に紡ぐ「真の成長パートナー」へと進化できるか。その「目利き力」と「伴走力」が、これからの競争力を左右します。
- そして、私たち専門家へ。私たちは、この変革の「案内人」であり「触媒」です。企業の情熱と、金融機関の論理を繋ぐ翻訳者として、客観的な評価と説得力のある戦略を提供する。特に、主観が入りやすい事業の将来性を評価する上で、私たちが研究する「事業性評価ツール」のような客観的アプローチは、ますますその重要性を増していくでしょう。
この記事が、皆様にとって、未来に向けた第一歩を踏み出すための羅針盤となれば、これに勝る喜びはありません。
変化は常に、挑戦する者にとって最大の好機です。未来は待つものではなく、自らの手で創り出すもの。さあ、この歴史的な転換点をチャンスに変え、未来志向の企業金融を、共に創り上げていきましょう。