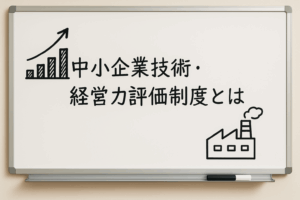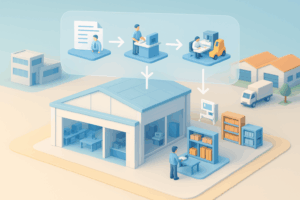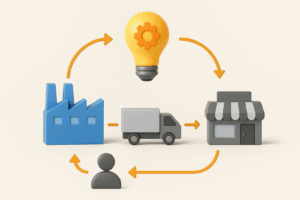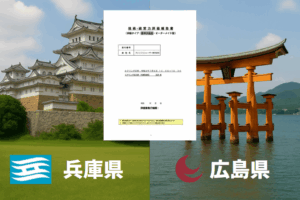前回は主として社長の経営力や経営陣の体制を見てきました。
今回は最後の評価項目である②人材・組織体制をご紹介します。
(4) 経営力 ②人材・組織体制
あらためて評価書に記載されている「②人材・組織体制」の内容について見てみましょう。
事業遂行のための人材が確保されており、円滑な組織運営ができているか評価した。組織と個人の能力向上のための教育訓練や資格取得に 取り組んでいるか、IT構築が出来ているかも評価した。
実際の評価書では以下のような項目が記載されます。
・組織図と人材に関する項目
・採用の方法
・教育の方法
・評価・処遇の方法
この他、有資格者が重要な業態であれば「資格者のリスト」等、主として人材、組織について評価をしていきます。
組織図と人材に関する項目
組織図を掲載するとともに、どのような組織機能があり、どのように稼働しているかを記載します。また、勤めている方の年齢構成や男女比、職場環境の状況や離職率等についてもこの項目で触れられることが多いです。
また、就業規則などの規定類について言及する評価者もいます。
規則等は法令に遵守する必要がありますが、更新等が滞っている中小零細企業はたくさんあります。それだけで2にするには実態として厳しいと思うので、次のようなケースでなければ私は注意喚起にとどめています。
①明確な法令違反が運用されている
法改正で過去の規定が×となった状態ですが、運用は現行法を守っているのであれば、「更新しましょう」という注意喚起でとどめます。
ただ、現行法に引っかかる運用をしていれば「それはダメ」と指摘し、そのような事案が散見されるようであればそれだけで2も仕方ありません。
②会社としての総務や経理部門を持つ規模である
会社としての体をなしているのであれば、ある程度規定は整備・更新されていることが必要です。そのため、規模に比べてあまりにもずさんであれば2もやむなしです。
個人的には親族以外の従業員が、正社員中心の会社であれば10人以上、パート中心の会社でも30人以上の規模であれば事務部門もそれなりにしっかりした体制が必要だと思います。
採用・教育・評価・処遇
採用の方法
人材採用の方法や採用担当者が誰か等の体制を記載します。採用の際に工夫されていることがあれば、その工夫も記載します。
昨今、非常に採用難の会社が多いですが、その中でも希望者が殺到するような会社もあります。そうした会社の場合は、なぜそのように希望者が集まるのかを説明します。
教育の方法
従業員の教育方法や教育を担う組織体制について記載します。
中小零細企業ではOJTと書くことが多いですが、研修や独自のテストなど、どのような形で人材育成に取り組んでいるかを紹介し、評価します。
評価・処遇の方法や体制
人材をどのように評価し、どのように評価を処遇に反映しているかを記載します。評価シートや定期的な面談等、企業が実施していることがあればその内容と評価を記載します。
個人事業の評価について
この項目ですが、社長一人で行っている事業や法人ではあるものの、社長一人、事務手伝いに社長の配偶者一人、あとは協力業者というような実質個人事業では評価がしにくいというものがあります。
この場合、人材・組織というものがほぼ無いわけですので、無いものは評価のしようがなく消去法で「3」と評価するのが妥当だと思います。
私の場合は社長の今後の意向を聞き、組織として拡大していきたいという希望があれば、今後組織体制を整えていく必要があるという形で、アドバイスを記載しています。
サンプルの内容の解説
ここからはサンプルを見ながら内容を解説していきます。
サンプルは前回と同じ企業になります。
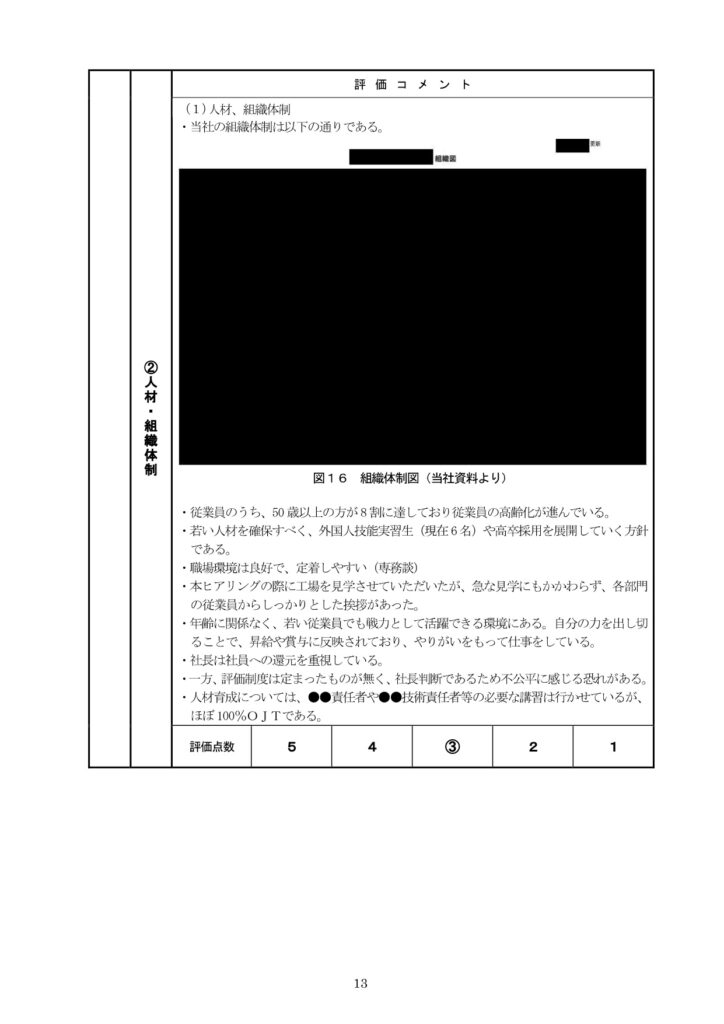
(1)人材組織体制
・組織体制図
組織図を掲載していますが、大きな問題もなくシンプルな構造(サンプルは黒塗りですが)であるため、細かな説明はしていません。
・年齢構成の紹介
50歳以上の方が8割と従業員の高齢化について課題として示しており、そのために会社がどのような対策を検討しているかを記載しています。
・社風について
職場環境が良好である点と、実際に現地を確認した評価者として体感した状況を記載しています。また、仕事に対して挑戦を奨励する社風であることも記載しています。
・教育・評価・処遇
評価制度の不備を指摘しています。また、人材育成も必要な講習以外はOJTという典型的な中小製造業です。
全体としては良くも悪くも中小零細企業の製造業という状況であるため「3」と評価しました。
本項目で技術・経営力評価における各評価項目の説明は終わりです。
10回にわたりお付き合いいただきありがとうございました。