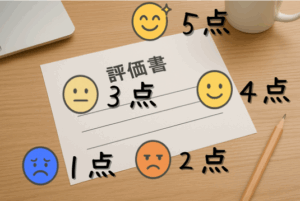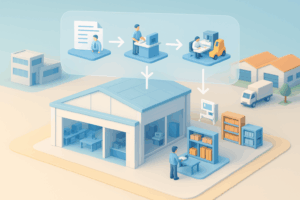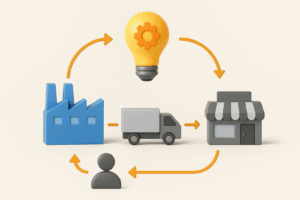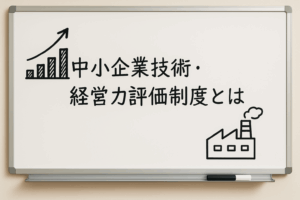前回は中小企業技術・経営力評価制度の書き方として、①新規性・独創性の内容について確認しました。今回は同じく製(商)品・サ-ビスの中の②優位性とその維持継続を見ていきましょう。
(1) 製(商)品・サ-ビス②優位性とその維持継続の内容
あらためて評価書に記載されている「②優位性とその維持継続」の内容について見てみましょう。
評価対象事業の競合相手に対する優位性およびその維持継続について評価した。製品・サービスの商品性だけでなく技術力、営業力、ブランド力、知的財産なども対象とし、外部資源の活用なども評価した。
実際の評価書では以下のような項目が記載されます。
・競合と比較した製品やサービスの特徴や優位性
・特徴や優位性の源泉とその維持継続のための取組み状況
こうした内容を網羅しながら優位性と維持継続について評価をしていきます。
シンプルに製品やサービスの強みがあるか?
何と言ってもシンプルに製品やサービスに強みがあるかどうかが評価のポイントです。この強みというのは自己満足ではなく、競合他社と比べて優れているか、お客様のニーズを捉えているか、と評価対象企業の収益の源泉となるものでなければなりません。
競合他社と比較してどうかという点は、評価を行う上で重要です。これを怠ると、社長のインタビュー記事となり評価とは言い難いものになります。特に優れた会社ほど、きちんと自社の製品・サービスの競合と比較したポジションを把握しており、こうした情報を引き出すことも専門家の重要なスキルです。
逆に「何となく自社の方がスゴイ、よく知らないけど」という社長もいるので、こうした会社には特に専門家としてしっかりと調べ上げて評価する必要があります。
またビジネスですので、お客様のニーズを捉えたものであるかも大事です。商品やサービスに対し社長のこだわりが強くなり過ぎた結果、「その機能は競合他社より優れている。ただしお客様のニーズはそこにない」というようなケースもあります。 もちろんニッチ市場で力を発揮することも中小零細企業の戦略の一つですが、会社を維持・継続させることができる収益を確保できるレベルのニッチ具合でなければ、ただの趣味で終わってしまいます。
製品やサービスの提供体制に持続性はあるか?
ここまで見てきた製品・サービスの強みは現在の話でしたが、維持継続については将来の話です。中小零細企業でよくあるケースですが、社長がとても優秀な技術者で開発、製造に八面六臂の活躍をしており、当社に明確な強みを形成しています。
しかし、この社長がいなくなれば強みはすぐに消失してしまうというケースです。
この社長がまだ30代や40代と若いのであれば、これから仕組化や技能承継の時間がありますが、70代の社長である場合、維持継続と言う点では非常にリスクが高いです。 この項目では、強みを維持・発展させていくための取組みをどのようにしているのか、そもそも実施しているのかを含めて評価します。
サンプルの内容の解説
ここからはサンプルを見ながら内容を解説していきます。
サンプルは前回と同じ企業になります。

(1)当社の優位性
まずは当社の製品やサービスに強みがあるかどうかを記載しています。サンプルでは「当社の強み」として製品並びに製品群にあるとし、評価対象会社の専務からの情報ではありますが、同業他社と比べてどう優れているかを記載しています。
さらに、製品並びに製品群の強みを形成できている理由として、販売網や生産体制への言及を行い、最終的にお客様のニーズを捉えたものであるとして「取引先企業の利便性につながっている」と評価しています。
(2)維持継続
当社の強みについて継続性があるものか、そのための取組みはおこなっているかを記載しています。
サンプルでは当社の強みを維持すべく、「不定期ではあるが新製品を展開している」という現状を記載しています。
また、開発上の強みとして販売先を記載し、それがいかにその後の販路拡大・定着につながるかを説明しています。
そして後半では、「不定期ではあるが」という状況説明をしています。計画的な開発が行われていないことや実質的に社長一人に依存していることから、製品開発体制に課題があると結論付けています。
まとめると、優位性とその維持継続という項目全体では、明確に強みと評価できる一方で、その維持継続については課題があるとして評価点数を「3」としています。
次回は「(2)市場性・将来性 ①市場規模・成長性」を紹介します。